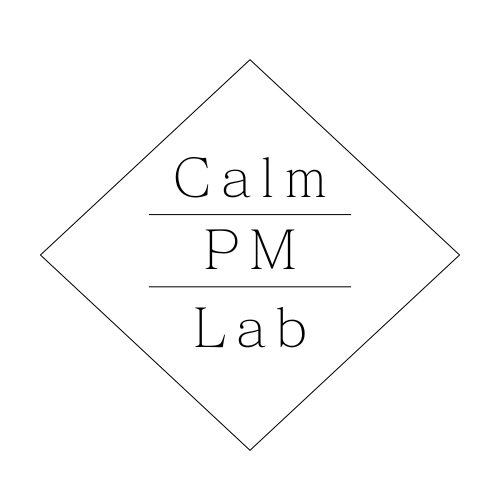PMが忙しそうにしているチームは、実はとても危険です。
もちろん仕事熱心なのはいいことに見えるかもしれませんが、「PMが忙しすぎる状態」はプロジェクト全体の余白を奪い、柔軟性を失わせ、変化に耐えられない状態をつくり出します。
Calm PM Labでは、あえて言います。
**「PMは暇そうであるべき」**だと。
忙しいPMは、信頼されない
PMがいつも慌ただしくしているチームでは、メンバーはこう感じはじめます。
- 「このプロジェクト、大丈夫かな?」
- 「PMに相談しづらいな」
- 「レビューが返ってこないから自分で何とかするしかないか」
PMが忙しそうにしていることは、安心感とは真逆の印象をチームに与えてしまうのです。
PMが余裕なくしていると、プロジェクトは全体として詰まりやすくなり、ボトルネック化します。
忙しさの演出は、マネジメントの放棄
PMが忙しいということは、プレイングマネージャーとして自分のタスクに埋もれている状態が多いです。
- 指示が遅れる
- 判断が雑になる
- フィードバックができない
- 全体の変化に気づけない
こうした状況は、チームの健全な運営を阻害します。
PMは、自分が「仕事をしている感」に酔ってはいけません。**本当の仕事は、“余白をつくること”**です。
“余白”のあるPMが、変化を可能にする
トム・デマルコの著書『Slack』の冒頭に、象徴的なたとえ話があります。
1〜9の数字が書かれたピースで構成されたパズル。
すべてのマスが埋まっている状態では、ピースを動かすことはできない。
どこか1つ、余白があって初めて、並べ替えや変化が可能になる。
このたとえは、プロジェクトにも当てはまります。
全員がフル稼働している状態では、変化に対応することはできない。
効率100%の状態は一見理想に見えますが、変化の余地がゼロであることを意味しています。
それは、柔軟性を失い、問題が起きたときに崩壊する危うさをはらんでいます。
ダーウィンの言葉にもあるように、
「生き残るのは、最も強いものではなく、最も変化に適応できるもの」
PMには、変化を見越した余白をつくるマネジメントが求められています。
忙しそうだと、人が寄ってこない
PMが常に何かに追われていると、メンバーは相談を遠慮するようになります。
その結果、こうしたリスクが高まります。
- 情報共有が減る
- 小さな問題が発見されない
- チームが孤立し、サイロ化する
- 「自分で何とかしなきゃ」という個別最適が広がる
このようにして、PMはチームの目や耳を失い、プロジェクトは“静かに悪化”していきます。
忙しさが、デスマーチの予兆になる
余裕がないPMは、いざというときに以下のような致命的な判断ミスをしやすくなります。
- リスクに気づけない
- 想定外への対応が遅れる
- 判断が後手に回る
- 責任が取れず、曖昧なまま走り続ける
こうした「判断の鈍化」と「状況の見逃し」は、プロジェクトを“終われない状態”に追い込み、デスマーチを招く要因となります。
おわりに – CalmなPMは、プロジェクトの守護神
PMが「暇そう」であることは、無能の証ではありません。
“全体を俯瞰している”“変化に対応する余白がある”という強さの証です。
- 忙しそうなPMは、チームのボトルネックになる
- 余裕のあるPMは、チームの安心と柔軟性を担保する
プロジェクトの成功とは、「常に全員が頑張ること」ではなく、変化に耐えられるしなやかさを持つこと。
だからこそ、Calm PM Labはこう提案します。
PMよ、あえて“暇そう”であれ。
それが、チームを守り、プロジェクトを成功に導く近道なのです。