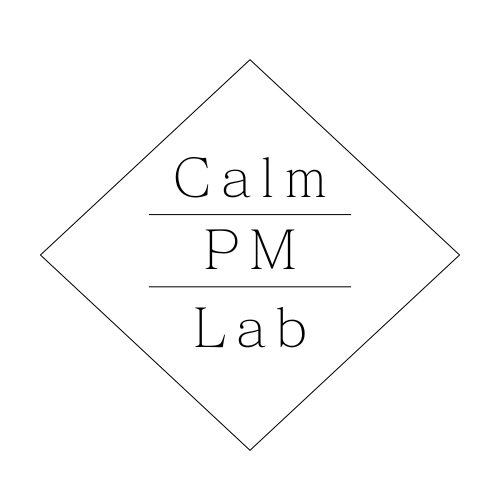情報が揃ってから意思決定できることは稀
意思決定に際して、必要な情報が出揃っていることは極めて稀です。ほぼ"無い"といってもいいかもしれません。そもそも、前回の記事で書いたように、人間の認知能力には限界がある以上、どこまで情報の拡充を目指してもなんらかの不足は必ず発生するのです。
つまり、意思決定とは常になんらかの不足がある状況下で行う行為です。有体に言えば、常に“勇気”が求められる行為です。ですので、少なくとも情報が足りないことは意思決定をしないことの理由にはならないのです(もちろん、その時点では意思決定をしないという決定も十分に一つの意思決定になり得ます)。
完璧主義は遅延を生む
意思決定に際して、必要な情報が全て揃うことはほぼ無い。この認識があれば、情報の欠如を理由に意思決定を回避することを避けられます。
多くの人が誤解しているのは、意思決定という行為には絶対的な正解があると考えていることです。現状認識に限界がある以上、当たり前ですが未来予測にも限界があり、故に、絶対的な正解など求めるべくも無いのです。必要な情報が揃えば、完璧で完全な意思決定ができると考えるのは間違っています。それはユニコーンのような架空の存在なのです。
意思決定に関して言えることはたった二つです。一つ、完璧な意思決定など存在しない。一つ、完璧を期すれば遅延が生じる。存在しないものを求め続ければ、遅れ続けるだけです。
曖昧な中でどのように一歩を踏み出すか?
決めることです。正解を選び取るのではなく、選び取った選択肢を正解にしていくことです。とはいえ、これは典型的な言うは易しでもあります。それに、なんでもかんでも「えいや!」で決めるわけにもいきません。
そこで私が心掛けているポイントをいくつか挙げておきます。
- 撤退基準を決めておく
- フィードバックを積極的に求める
- スコープを細かく区切る
撤退基準を決めておく
オフェンスよりもディフェンスを固めることを優先しましょう。意思決定自体は思い切って行うしかありませんが、それによって特定の状況に陥ったら撤退や見直しを行うことをあらかじめ決めておくのです。正解は誰にも分かりませんが、生物としての人間にはそれが致命傷かどうかは判断できます。
フィードバックを積極的に求める
前回書いたようにフィードバックを得ることによって、人間はより現実に迫った認識を持つことができるようになります。もちろん、それでも限界はありますが、フィードバックを多く得ることで、より蓋然性と妥当性の高い判断がしやすくなるのは確かです。
スコープを細かく区切る
意思決定のスコープを細かく区切り、振り返りの頻度を高めます。潜水艦は艦内が多数のキャビンで区切られ、被弾などでどこかが浸水してもそのブロックを閉じて切り離してしまうことで艦全体が沈んでしまうことを回避できる仕組みになっています。意思決定も同様にその影響範囲を細かく区切る、または、定期的に見直すことで誤った判断をした場合の悪影響を最小化できます。