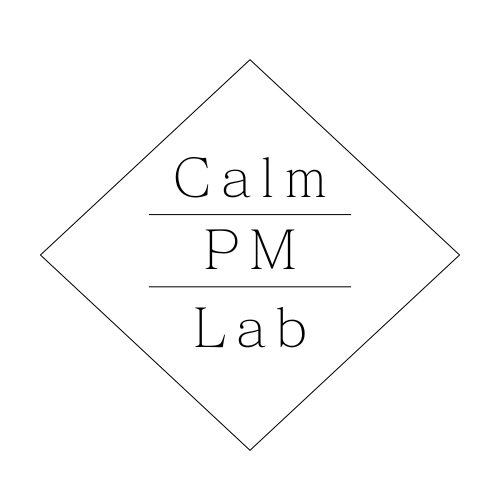効率化に夢を見る社会
「効率化すればラクになる」「無駄を省けば幸せになる」。私達の身の回りにはこうした言説が溢れています。溢れているどころか、私たち自身がそれを正しいこと、幸福につながることだと信じて、実際に口に出し、実現しようとすらしています。
しかし現実には、効率化すればするほど、心が疲弊していく場面を数多く見てきました。自動化や高速化が仕事を楽にするのは一時だけで、空いた時間には別のタスクがすぐに詰め込まれます。別のタスクが詰め込まれるならまだ良い方で、仕事自体がなくなってしまうことも多々あります。それでも、もっと、もっとと何者かに追われるように私たちは効率化を止めることができません。
「効率化」の本質
効率化とは「最小の入力で最大の出力を得る」ことです。しかし、人間の幸福は「最大の出力」に比例するとは限りません。「最大の出力」に比例するのは人間の幸福ではなく、競争の勝率です。私たちが効率化を止められないのは、競争から降りることができないからです。不幸なのは、競争が源泉である以上、求められる成果は「絶対的な量」ではなく、他者と比べての「相対的な量」になるという点です。つまり、どこまで行ってもゴールがない。これは、つらいです。
しかしながら、競争に掛け金を置いている立場からすると、競争で勝つことは絶対に必要なことになります。なぜなら、競争は勝者が総取りする構造になっているからです。負ければ全てを失うというゲームにおいて、勝つことを求めないことは不可能です。故に、資本家や顧客など資金を提供(Bet)する立場に立てば、競争は望ましいどころか、なくてはならないものになるでしょう。
重要なのは、元々「効率化」というものは働いてサービスを提供する者のために存在する概念ではないということです。
非効率にこそ、人間性が宿る
競争に勝つためには「効率化」が必要です。しかし、「勝ち続ける」ためには「非効率」が必要だということは見落とされがちです。
変化できるものが生き残る。ダーウィンが言うように変化するためには、ギチギチに最適化、効率化されていては変化のしようがありません。変化し、生き延びるには"ゆとり"が必要なのです。
「勝ち続ける」ということは、つまり「生き延びる」ということです。目の前の競争に一時的に勝つために"ゆとり"を削って最適化した場合、生き延びる可能性は低くなる。生物は短期の生存と長期の生存、両方を生きなければ短命に終わるのです。
雑談、寄り道、遠回り、手間暇、そして休息。非効率で一見無駄に見えるものにこそ、信頼や共感、学び、創造、変化の余地が宿っています。
「幸せ」の単位は時間ではない
タイパ、コスパといった言葉が巷間に流布して久しいですが、「効率化」と「幸せ」は別軸であることが忘れられているように見えます。考えるまでもなく「幸せ」とは(測るとするならば)“誰と・どう過ごしたか”で測るものであり、効率化とは無関係のものです。
タイパ、コスパを追求するのが間違っていると言いたいわけではありません。ただ、その道は「幸せ」とはリンクしていないし、「生き延びる」力を削ぐことになりがちであるという自覚はしておいた方が良いという話です。
効率化は道具であり、目的ではない
PMがなぜ効率化に疑義を持つべきなのか?請け負ったプロジェクトを成功させることだけに集中すれば良いのではないか?そう考える向きもあるかと思います。
もちろん効率化は悪ではありません。しかし、それ自体を目的にすると必ず歪みます。
目の前のプロジェクトの意義が「効率化」だけであるなら、手段が目的化している可能性を疑った方が良いです。また、そのプロジェクトのためにあらゆる「ゆとり」を削る判断をする前にPMとして「それはチームが幸せになる選択か?」という視点を忘れないようにしてください。
プロジェクトが終わっても、人生は続いていきます。完了したプロジェクトの後に何も残らなければ、次の挑戦に向かう力を失ってしまうかもしれません。