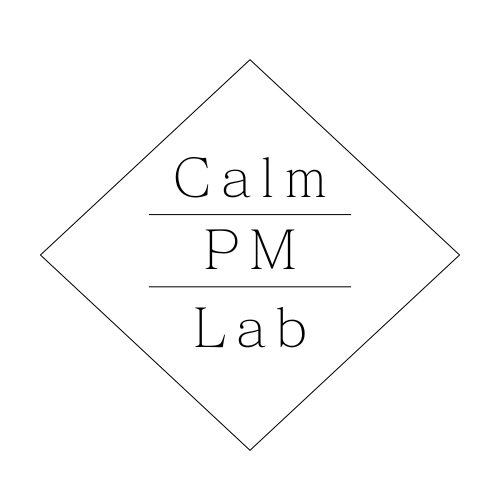プロジェクトがデスマーチに陥る最大の原因のひとつは、「終わらせ方を決めていないこと」だと私は思っています。
プロジェクトには始まりがあり、そして、本来は終わりもあるべきなのです。
しかし、現場ではしばしば「終わり」が曖昧なまま、なんとなく継続されているプロジェクトが存在します。
リリース後も追加要望が止まず、関係者の誰もが「これ、いつまで続くの?」と口には出さずとも感じている。
そうした“終わらないプロジェクト”は、徐々にチームを疲弊させ、やがては士気の低下や離脱者の増加を引き起こします。
「終わり」は自然にはやってこない
プロジェクトの終了は、自然発生的には起こりません。
PMが明確に意志をもって「ここで終わらせる」と定義しなければならないのです。
それは、成功裏に終わる場合も、中止や撤退といった形になる場合もあります。
「うまくいかなかったからやめる」ことをネガティブに捉えすぎて、なんとなく延命を続けてしまうことが、結果的にプロジェクトを腐らせてしまう。
終わらせる覚悟を持てるかどうかが、PMの力量なのだと思います。
成功とは「完了」ではなく、「納得のいく終わり方」
プロジェクトの成功とは、「完了」や「納品」ではなく、関係者が納得できる形で物語を閉じることです。
- 目的が果たされた
- リソースを打ち切ることが合理的と判断された
- 顧客に最大限の価値を届けられるところまで到達した
こうした“終わらせ方の合意”が得られていれば、それは十分に成功と呼べるのではないでしょうか。
「終わらせられないPM」は、誰を守っているのか?
プロジェクトを終わらせないPMは、しばしば「関係者のため」「会社のため」と言います。
けれどその実、自分自身の言動の一貫性を保つことを、プロジェクトの価値よりも優先しているように見えるときがあります。
つまり、視点がチームや成果ではなく、自分自身に向いてしまっているのです。
一貫性よりも、変化に応じて方向を変える柔軟性の方が、プロジェクトにははるかに大切です。
PMはその場その場で、最も合理的な判断を下す責任があります。
撤退もまた、戦略の一つ
撤退という選択肢に、もっとPMは自信を持っていいと思います。
もちろん、無責任に手放すのではなく、「この先に合理性がない」と判断する冷静な視点を持つことが前提です。
むしろ、無理に続けるほうが、よほど無責任です。
エンドレスに続くプロジェクトに巻き込まれるメンバーの疲弊を思えば、「この方向性はもうやめよう」と言えるPMこそが、チームを守る存在になり得ます。
終わり方がチームを救う
プロジェクトの終了を設計することは、PMにしかできない仕事です。
他の誰かがやってくれるわけではありません。
- どこまでやれば終わったとするのか
- どんな条件で中止するのか
- 終了時にどのようにメンバーと成果を振り返るのか
こうした設計がされていれば、チームのエネルギーは消耗しすぎることなく、次のプロジェクトへと移行していけます。
チームを育てることがPMの仕事
PMの仕事は、プロジェクトを成功させること——
…だけではありません。
チームを育てることこそが、PMのもっとも本質的な仕事だと私は考えています。
目の前のプロジェクトに全てを注ぎ込むあまり、チームを疲弊させ、心中させてしまっては意味がありません。
そのプロジェクトが思うようにいかなかったとしても、チームが生き残り、成長していれば次があります。
プロジェクトには寿命がある。けれど、チームには未来がある。
その未来を潰さないために、「このプロジェクトはここで終わらせよう」と決断する勇気がPMには必要なのです。
終わらせることでチームを守り、次に備える。
それが、プロジェクトマネージャーにしかできない仕事のひとつです。