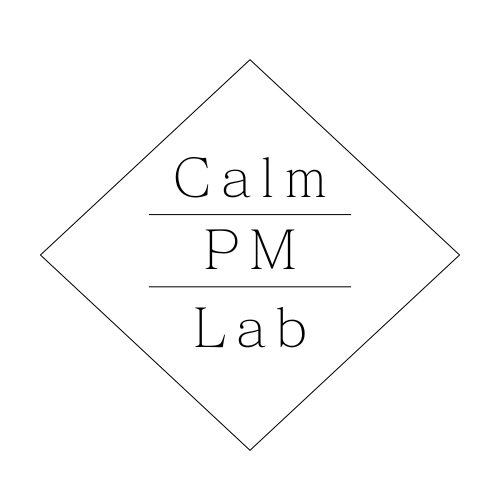社内の仕事が行き詰まったとき、外に目を向けることがブレイクスルーのきっかけになることがあります。
プロジェクトマネージャーとして、自分の経験や社内の価値観だけで判断することには限界がある——それを日々痛感しています。
今回は、「なぜ社外に知見を広げることが、社内の仕事にもプラスになるのか」を、いくつかの観点から整理してみます。
1. 視座が上がると、見える問題も変わる
同じ社内にずっといると、知らず知らずのうちに「常識の檻」に閉じ込められてしまうことがあります。
他社のやり方や他分野の工夫に触れることで、「あれ?これ、もっと別の方法があるんじゃないか?」という疑問を持つことができます。
- 社外のPM勉強会に参加して知った進め方
- NPOや副業での関わりを通じて学んだ意思決定の違い
- 他業界のトレンドや失敗事例
こうした“違い”を知ることで、今ある課題が単なる「社内の常識」から生まれているだけなのかもしれない、という新たな見立てが得られるのです。
2. プロジェクトの価値を相対化できる
社内に閉じていると、自分たちのプロジェクトを過剰に「絶対視」してしまいがちです。
「このプロジェクトは絶対に成功させなければならない」
「今やっていることが、会社にとって最も重要であるはずだ」
こうした思考は、判断の柔軟性を奪い、時には撤退や方向転換といった必要な判断を妨げます。
社外のプロジェクトや潮流を知ることで、今自分が取り組んでいることが、社会全体の中でどんな価値を持ちうるのか、冷静に評価する目が養われるのです。
プロジェクトを“神聖化”してしまうと、PMとしてのバランス感覚を失います。
価値を相対化する視点は、その歯止めになるのです。
3. 外の視点は「比較」を生み、「分析」につながる
比較しないということは、言い換えれば分析しないということとほぼイコールです。
なぜなら、比較とは物事を要素に分解し、差異に着目する行為だからです。
社内に閉じていると、当然ながら比較の頻度は減ります。
その結果、分析の深度も浅くなり、状況把握や意思決定の精度が下がってしまう。
PMに求められるのは「分析して判断すること」です。
そして、そのためには**比較対象としての“外部”**がどうしても必要です。
4. 持ち帰って応用する力が社内を動かす
外で得た知見をそのまま社内に導入することは難しいかもしれません。
でも、「なぜそれがうまくいっているのか」「うちでは何が足りないのか」という問いを通じて、自社用にカスタマイズされたヒントが生まれます。
- 会議運営のファシリテーション
- ツールの使い方
- 情報共有のルール
- レビューや振り返りの習慣
小さな変化でも、それが“改善の文化”を根付かせる第一歩になることがあります。
5. 自分が変わると、組織にも良い波及がある
外部から得た知見をきっかけに自分が変わり、その変化を通じてチームやプロジェクトに良い影響が及ぶ。
この正の連鎖が、「PMとしての価値」を内外に広げていく力になります。
結果として、以下のような副産物が得られます。
- 思考の柔軟性が上がる
- 会話の解像度が上がる
- 信頼されるPM像に近づく
おわりに:外を見ることは、内を見るレンズを手に入れること
「社外に出る」ということは、遠くを見ようとすることではなく、自分たちの立ち位置をクリアにするための“鏡”を手に入れることです。
視野を広げることは、冷静な比較を可能にし、分析の精度を高め、結果としてより良い判断につながります。
そして、社内のプロジェクトの価値を過度に絶対視せず、柔軟に導くためにも、外部の視点が必要なのです。
外を見ることで、内をより深く理解できる。
それはPMという職業において、とても大きな武器になります。