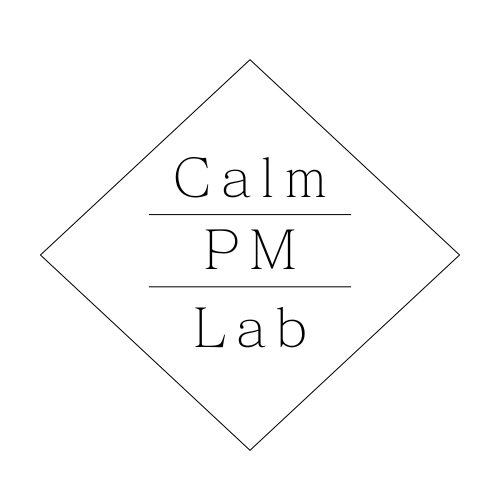うまくいく前提で始まる計画は幻想
プロジェクトはもちろん成功させるために行われます。プロジェクトの目的を達成して、なんらかのアウトカムをもたらす。そのために期間限定で行われる活動がプロジェクトです。ですので、プロジェクトはその企画の段階から"成功"に目が向けられている活動といえます。
しかしながら、実際にプロジェクトを成功させるためには、むしろその逆。"失敗"に目を向けなくてはなりません。プロジェクトを進行する中で発生する、大小様々な失敗要因を回避するなり、対処するなり、潰すなりしていくことがプロジェクトマネジメントの実態と言えます。なぜなら、放っておいても成功するような活動であればそれはプロジェクトとして意識されないか、または他者や他社が既に行っていることであるはずだからです。
つまりプロジェクトという活動にはもう一つ特徴があって、それはもともと成功する確率が低い活動である、ということなのです。ですので、そのマネジメントにおいては"失敗"をいかにコントロールするか?が最も重要なこととなるのです。
「失敗前提」の計画がチームを安心させる
失敗すること、困難に遭遇すること、予想外のトラブルに巻き込まれること。プロジェクトマネジメントという活動が"失敗"のコントロールであるとすれば、こうしたことが発生することを前提に計画を立てることがPMの仕事であることは自明です。
つまり、「〜がうまくいけば次は〜が進む、そこに〜を加えれば理想的な結果が得られる」といった、“成功の連鎖”を前提にした発想はPMにとって危険です。
逆にPMがとるべきは、「〜が起きたら遅延する」「〜と重なれば予算が吹き飛ぶ」「競合が〜すればプロジェクトの意義が消える」といった“失敗前提”の積み上げです。その意味では、私はプロジェクトを進めたがっている人物は実はPMとして適任では無いのかもしれないとも思うことがあります。
PMは、プロジェクトの"失敗"をコントロールする仕事だと言いました。そして、"失敗"をコントロールするためには、まず"失敗"要因をリストアップする必要があります。ありとあらゆる失敗シナリオを想像して、想定して、備えるのです。
そうして、多様な失敗シナリオを想定した計画が存在することがチームを安心させます。「きっと上手くいくから大丈夫」という言葉は気休めにはなっても、安心はさせてくれるわけではありません。想定外のトラブルも発生しますから、PMが完全に"失敗"をコントロールできるわけではありません。しかし、PMが可能な限り失敗を想定し、その上で立てた計画であることがわかっていれば、チームはリスクを勘案した上で、その計画に納得して掛け金をおけるのです。
段階的な修復可能性(リカバリープラン)の重要性
当然ですが、失敗シナリオを想定するだけでは"失敗"は回避、対処できません。あわせて、各シナリオに合わせたリカバリープランを練っておく必要があります。しかしながら、"失敗"の可能性は大小、無限に転がっているため、全てに対応するプランを持っておくことはできません。
そのため、主要な失敗シナリオのリカバリープランを用意したら、後はプロジェクトを進めながら都度、定期的に、その時のプロジェクト状況を踏まえて段階的なリカバリープランを考える必要があります。重要なのは"失敗"の可能性に常にフォーカスして、リカバリープランを考え続けるということなのです。