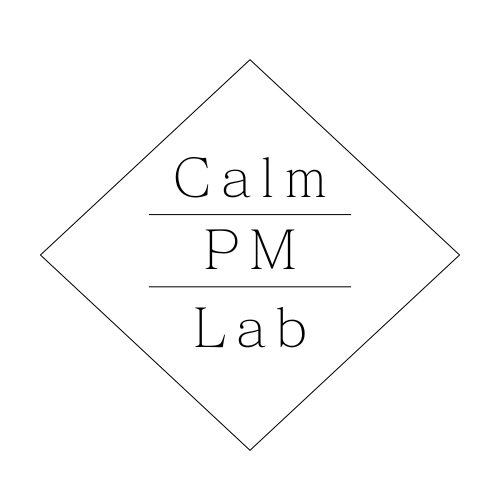人間の認知には限界がある
当たり前ですが、人間は全知全能ではありません。どんな人間も、その知識には限界と偏りがあり、バイアスがあり、好みがあり、機嫌の良し悪しがあり、能力は凸凹です。したがって、自身や自組織が置かれた状況、現実を正確に把握して判断ができる人間はいません。一人も。
そのため、他者からみると、または後になって考えると信じられないような愚かな意思決定が行われることがありますが、これは異常なことではなく、人類としては常態なのです。見えている範囲が偏っているし、限りがあるのですから、当たり前です。
では、どうすれば良いのでしょうか?
一つの答えとしては、一人では限界があることを認めることです。つまり、他者からの、それも多様な他者からのフィードバックを求めるということです。
フィードバックを得ることで現実をみる
一人一人が把握できる"現実"には限界があります。そこで、多様なメンバーによって対象を様々な軸から評価することによって、"現実"を浮かび上がらせる。これが最適解になってきます。
もちろん、「群盲像を撫でる」の例えではないですが、どんなに多様なメンバーによるフィードバックを集めたとしても、結果的にそれが現実とイコールになることはありません。しかし、近づくことはできる。少なくとも一人でフィードバックなしで判断するよりは、現実に基づいた判断が行いやすくなります。
多くの場合の判断においては、それが現実と言えなくても、多様なフィードバックによって現実に迫るだけで、現実に対する十分な理解と解像度を得られることも多いため、実用上は問題ないことも多いのです。
フィードバックによる認識のクリアさは、肌感覚ではありますが、ある程度の人数を超えると指数関数的に効果が逓減していくように感じます。問題の規模によりますが、だいたい5人程度もフィードバックを得られれば十分な効果を得られるとみて良いでしょう。ジョエル・スポルスキの言う「廊下での使い勝手テスト」が有効である理由も肌感覚と一致します。
現実に立脚したプロジェクト運営を
ジャック・ウェルチが部下のマネージャたちに説いたという言葉
「現実を直視せよ。‥‥世界をありのままに見よ。こうあってほしいという目で見てはならない」
現実に立脚しなければ、当然ですが、プロジェクトは迷走します。空中でリンゴを手放せば落ちるように、当たり前のことです。しかしながら、前述の通り、人間の現実認知能力には限界があります。そのため、現実に立脚するためには、少なくとも現実に"近しいもの"に立脚するためには、フィードバックを積極的に求める必要があるのです。
つまり、反論、反対意見、懐疑、といったものを奨励する必要があります。PMが自分に任せておけば大丈夫だといった態度をとったり、方針に疑義を呈することを禁じるような態度や雰囲気を作っていると、フィードバックは生じず、プロジェクトの視界は一気に狭くなっていくのです。
暗闇の中でライトもつけずに車を運転して、無事に目的地に着けるとお考えなら——ぜひ、会社の銘柄を教えてください。私は全力で空売りします。