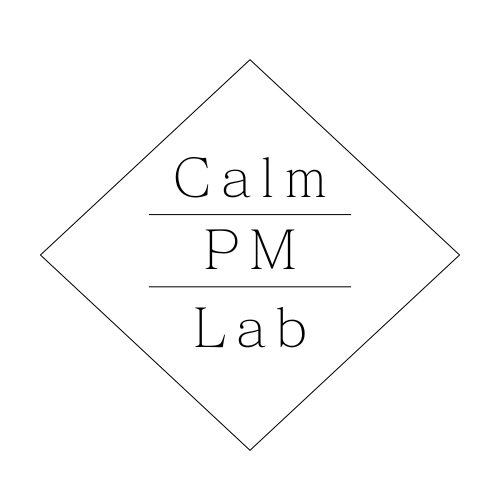本質的な価値を見失わないために
はじめに – AIがPM業務を補助する時代
最近では、ClaudeやChatGPTを使えば、要件定義の草案を作ったり、議事録を書いたり、メール文面を整えたりと、PMの業務の多くをAIが補助してくれるようになってきました。
タスク分解やWBS作成、会話ログからのTODO抽出など、「やろうと思えばAIに任せられる」ことがどんどん増えています。
では、そうした時代において、プロジェクトマネージャーという役割は、どう変化していくのでしょうか?
「代替される仕事」と「代替されない仕事」の違い
まずは、AIに向いている仕事と、向いていない仕事の違いを整理してみましょう。
AIが得意とするのは、定型化され、再現性が高く、インプットとアウトプットの対応関係が明確な作業です。
たとえば
- メール文章の整形
- 議事録の自動生成
- スケジュール表の更新
一方で、AIが苦手とするのは、曖昧さを含む文脈の解釈、人間関係の調整、複数の価値観のバランスを取るような意思決定です。
また、AIを「道具」として使う段階を超えて、今や「対話相手」として捉えることも可能になっています。
それでもなお、最終的な責任や意味づけは人間に委ねられます。
PMが持つべき“人間ならでは”の役割
PMの仕事には、数値や文書ではとらえきれない要素がたくさんあります。
たとえば
- プロジェクトに流れる空気を読む力(緊張感・不信感・期待感)
- 利害の異なる関係者を調整する「落とし所」力
- “正しいかどうか”ではなく、“納得されるかどうか”を判断する力
- 「誰が、なぜ、それをやるのか」を問い続ける姿勢
こうした力は、AIには模倣できません。
なぜなら、これらは人間の集団の中でしか発生しない、コンテキストと信頼のマネジメントだからです。
ゴールの定義と品質保証はAIに任せられない
特にPMの役割として重要なのが、「最終的にどうなっていれば成功か?」というゴールの定義と、その品質を担保する責任です。
この2つは不可分であり、要するに
最終的にどうなっていればいいのか、それを表明し、担保するのは人間であり、PMの役目である
と、私は考えています。
AIに何かを任せるということは、それを外部発注しているのと構造的には同じです。
つまり、これは従来から存在してきた、「納品物の品質をどう担保するか?」という問題に他なりません。
期待通りの成果物を得るためには
- 期待(ゴール)の明確化
- 指示の明確化
- 品質検査(レビュー・評価基準)の高度化
といった人間側のスキルが欠かせません。
これらのスキルは、AIを使いこなすために必要であると同時に、プロジェクトを“デスマーチ”にしないためにも不可欠です。
プロジェクトが炎上する最大の原因のひとつは、曖昧な期待・曖昧な指示・そして検収基準のなさによって、「後からやるべきことがどんどん増える」状態になることです。
AIとの連携が増えることで、この構造はより加速する可能性があります。
だからこそ、ゴールを定義し、品質を定義し、それを最初から最後まで管理し続けることが、PMにとってますます重要になるのです。
AIを活かしながら、人間としての価値を高めていくには
AIに仕事を奪われることを恐れるのではなく、AIに任せられることを積極的に任せることで、自分の価値を高めていくことが大切だと考えています。
たとえば、AIに議事録や要件整理を任せることで、
PMはそのぶん「誰がつまずいているか」「何を議論すべきか」に集中できます。
“効率化して得た余白”を、人間同士の対話に充てる。
それこそが、AIと共存するPMのあるべき姿だと思います。
そしてなにより、書くこと・考えること・語ることを手放さずに、
意味をつくる人間としてのPMでありたいと、私は感じています。
おわりに – 自動化されない自分の軸を持つ
AIはどんどん賢くなります。PMの作業も、どんどん“補助されるもの”になっていくでしょう。
だからこそ、自分がなぜこの仕事をしているのか、
このプロジェクトはなぜ存在しているのか、
その 「意味」と「目的」に向き合い続ける姿勢 が、ますます大事になってくると感じます。