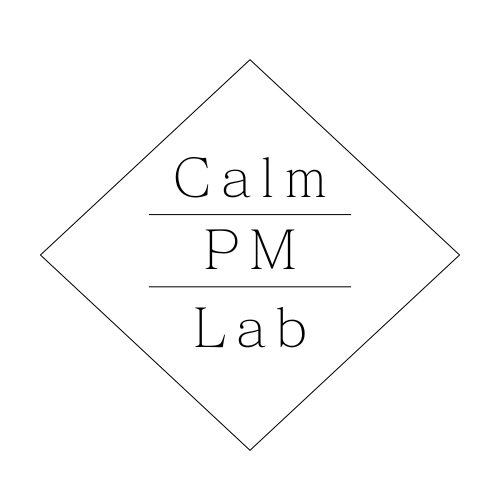はじめに – なぜ今このテーマなのか
ブログを再開して、あらためて実感していることがあります。
それは、「外の世界とつながること」の価値です。
プロジェクトマネジメントという仕事は、どの会社にも必ず存在します。
でも、会社の文化や業種によって、PMの振る舞いや重視されるスキル、成功とされる基準は驚くほど異なります。
私はこれまで、いくつかの組織でPMとして働いてきましたが、それでもなお「自分のやり方は、このままでいいのか?」という問いがついて回ります。
だからこそ、他社のPMとつながり、学ぶことを、もっと積極的に捉えたいと思っています。
他社のPMから学べることは何か
他社のPMと話すと、次のような違いが見えてきます。
- プロジェクトの進め方(スクラム、ウォーターフォール、ハイブリッド…)
- ドキュメントの粒度や共有のスタイル
- トラブル時の初動やリカバリの方法
- ステークホルダーとの距離感やコミュニケーションの濃度
しかし、こうした「方法論の違い」以上に重要なのは、“視座”の違いです。
たとえば、「プロジェクトの成功とは何か」という定義。
「関係者とどう信頼関係を築くか」という価値観。
そうした前提の違いに触れることこそが、学びの本質ではないかと思います。
なぜ学びにくいのか?
一方で、他社のPMから学ぶことには障壁もあります。
- 社内文化に閉じてしまう構造(「うちはうち」の空気)
- 「他社の方法は参考にならない」という思い込み
- 自分のやり方を否定されるような気持ちになる恐れ
これらは、すべて私自身も感じたことのある感覚です。
だからこそ、意識して“外”に出ることが必要です。
他社のPMの言葉に耳を傾けて初めて、自分の偏りや限界にも気づけるのだと思います。
PMが“越境”することの意味
他社のやり方を知ることで、「なぜ自分はこうしているのか?」という問いが生まれます。
これは、自分のPMスタイルを客観視するきっかけになります。
また、真似ることを通して、自分の個性が浮き彫りになるという側面もあります。
人は他者と交わり、他者を真似ようとしたとき、どうしてもうまく真似できない部分に直面します。
その“真似できなさ”こそが、自分の個性の輪郭を教えてくれます。
逆に言えば、自分が「これが自分らしさだ」と思っている多くのものは、時代や環境、世代、職業、性別、役割といった要素によって規定された“既製品”であることが多いのです。
だからこそ、人間は自分を知るために他者を必要とします。
他社のPMと交わることで、「自分を誤解していた部分」が少しずつ剥がれていく。
そしてその先に、本当の意味での“自分のスタイル”が立ち上がってくるのではないでしょうか。
変化の激しい時代において、学び続けられるPMは、環境が変わっても強い。
だから私は、どんどん越境していいと思っています。
おわりに – ブログを書く理由と重ねて
この Calm PM Lab は、もともと「自分の思考を整理するため」に始めました。
でも今はそれ以上に、「他社のPMと、ゆるくつながれる場所」に育てていきたいと思っています。
一人では見えないことも、他の誰かの経験と言葉を借りることで見えてくる。
それが、プロジェクトマネージャーという“実践者”同士の学び合いの良さだと思います。
私はこれからも、自分のために書くことを通じて、外とつながりながら学び続けたい。
そんな気持ちで、今日もブログを書いています。