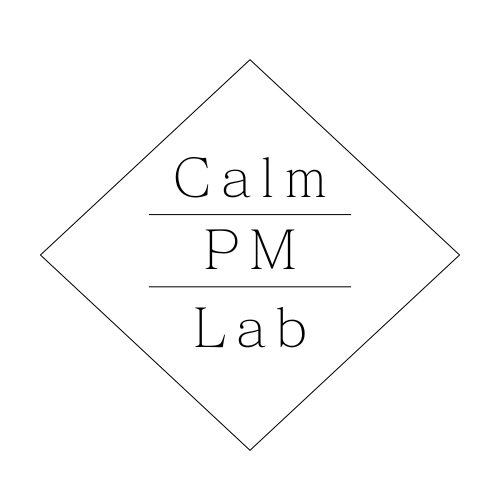「一つの会社に誠実に尽くす」という価値観に、疑問を持つようになりました。
プロジェクトマネージャーという職種は、もともと全体を俯瞰し、状況に応じて柔軟に判断を下すことが求められます。にもかかわらず、気づけば自分自身が「一社依存」状態に陥っていた。
これは明らかにリスクですし、本来PMが避けるべき構造ではないかと感じるようになりました。
一社依存は、極めて脆い構造
一社依存の問題点は、とてもシンプルです。
- 会社の業績が悪化すれば、自分の生活が直接的に影響を受ける
- 会社の評価制度が変われば、自分の価値も揺らぐ
- 人事異動や制度改定で、自分の希望が通らなくなる
自分がどれだけ努力しても、それとは無関係な外的要因で足元が揺らぐ。
そのことに対して、あまりにも無防備だったと、過去の自分を省みています。
そもそも会社は「取引先」にすぎない
このことに気づいたのは、「会社って“ご縁のあった取引先”にすぎないのでは?」という視点に立ってからです。
商取引において、一社依存が危険であることは常識です。
他に顧客がいなければ、取引停止=事業終了となってしまう。
ところが、こと自分のキャリアになると、このシンプルな理屈を見落としていた。
もちろん、会社に感謝する気持ちはあります。でもそれは、「親しき仲にも礼儀あり」と同じで、感謝と距離感は両立できるのです。
適切な距離感を持つということ
これは人間関係でも同じです。
深く関わりすぎると、相手への期待が過剰になりがちです。
ゼロ距離で依存し合うようなベタベタの関係では、お互いに苦しくなる。
ある程度ドライで、余白を保った関係の方が、結果的にうまくいくことも多い。
いや、むしろその方がほとんどの場合うまくいくとすら思います。
人には「自分の思い通りに動いてくれない」と理解して接するのに、
会社になると「察してくれるはず」「報いてくれるはず」と期待しすぎてしまう。
これは明らかに期待値のバグです。
会社も“法人”という名前がつくほどで、ひとつの「人」的存在と見るなら、
距離感を保ち、こちらの願望を押し付けすぎないことが、健全な関係の鍵です。
PMこそ「社内最適化」から脱却を
プロジェクトマネージャーという仕事は、組織内の調整が多く、知らず知らずのうちに「この会社だから通用するスキル」に最適化されていきがちです。
しかし、それがPMとしての本質ではないはずです。
- どんな状況でも構造を見立て、課題を整理し、合意を導く
- 異なる立場を橋渡しし、意思決定を支援する
それらは会社に依存しないPMの中核スキルであり、むしろ社外にこそ価値があるものです。
自立に向けた3つの問い
ここから抜け出すために、私は以下の3つの問いを自分に投げかけるようにしています。
1. 成果を「社外の言葉」で語れるか?
「部長職で年商5億のプロジェクトを統括」といった肩書きやスケール感よりも、
「混乱していた開発チームに共通言語を提供し、立て直した」
のような、本質的な成果の記述を意識する。
役職や社内評価ではなく、課題と価値の観点で語れるかどうかが重要です。
2. 外でも通用するスキルを意識する
- ファシリテーション
- 論点整理・構造化
- 言語化・共通理解の創出
- 合意形成・意思決定支援
こうしたスキルは、どの業界でも価値がある。
だからこそ、「社内で何ができるか」ではなく、「どんな文脈で価値を発揮できるか」という視点が求められます。
3. 「誰に・何を届けたいか」を考える
会社のために働くのではなく、誰かの役に立ちたいから働く。
その“誰か”の輪郭を、自分の言葉で語れるようになることが、PMとしての自立の第一歩になると信じています。
小さく外とつながる
一社依存から抜け出すといっても、いきなり転職や独立をする必要はありません。
- ブログを書く
- 他社PMと交流する
- オンライン勉強会に出てみる
こうした小さな越境が、実は自分の視野を大きく広げてくれます。
おわりに – PMこそ自立の視点を
会社はありがたい存在です。
けれど、それは「たまたまご縁があった取引先」という位置づけでもある。
全力で感謝しながら、でも、適切な距離感を忘れない。
そのドライさこそが、自分と会社、両方にとって健全な関係を築く鍵だと感じています。
「選択肢を持つこと」が、あなたの冷静さと、プロジェクトの安定を生む。
プロジェクトマネージャーこそ、そういう自分のマネジメントが求められているのではないでしょうか。