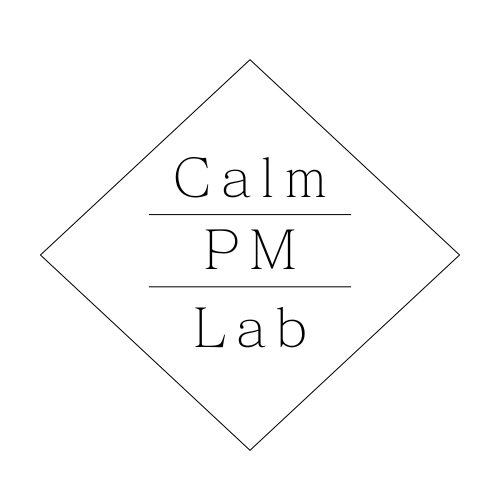プロジェクトにせよ、人生にせよ、私たちの前にはときに圧倒的な複雑さが立ちはだかります。何から手をつけたらいいかわからない。判断が判断を呼び、次の選択肢が見えない。
そんなとき、私は最近こう考えるようになりました。
「一つでいい。まず、一つだけ丁寧に解こう。」
if文の複雑さと現実の迷路
プログラミングにおけるif文は、条件が一つ増えるごとに可能性を倍にします。
1つなら2通り、2つで4通り、3つで8通り。組み合わせは指数関数的に増え続けます。
将棋盤に米粒を1粒ずつ倍々に置いていったという逸話があります。最初は微々たる量でも、後半になると天文学的な数になる。小さな分岐が連鎖的に全体へ大きな影響を与えるという点で、if文にも同じことが言えます。
そして、この構造は私たちの現実の問題にも似ています。
「あれも気になる」「これも判断しなきゃ」と条件が頭の中に積み上がっていくと、あっという間に「どこから手をつけていいかわからない」状態に陥ります。
しかし、その中の一つを解くことができたら──
それだけで、if文を一つ削除したのと同じように、全体の複雑さは半分以下に減るのです。
一つを解くことの力
私たちは「まだ9割残っている」と思いがちです。でも実際は、「最初の1つが一番影響力が大きい」ことがある。
- 一つの判断が、他の選択肢の必要性を消す。
- 一つの迷いをクリアにすると、他の迷いも整理される。
- 一つの判断が基準になり、以後の判断が自動化される。
からまった紐をほどくとき、最初の一手が正しければ、あとの結び目は驚くほどスムーズに解けていきます。
現実が変わる「風穴」としての一手
圧倒的な状況の前では、思考も、身体も、すくみます。
どこから取りかかればいいか分からず、立ち尽くしてしまう。
でも、そんなときこそ「一つを丁寧に解く」ことが現実に風穴を開けます。
- 複雑さが減る。
- 不安が減る。
- 見通しが立つ。
- 次の一手が見えるようになる。
それはたった一手に見えるかもしれない。
でも、それは全体の重みを根本から変えてしまう一手かもしれないのです。
おわりに
考えることを減らす、のではありません。
むしろ、考えるべきことと向き合い、一つ一つ丁寧に解いていくという姿勢こそが、複雑さを本質的に減らす力になります。
そして何よりも大切なのは、「最初の一つを解くこと」。
その小さな一手が、指数関数的にふくれあがっていた複雑さを現実に半減させ、
次へと進む力を与えてくれます。
あなたの目の前にも、きっと“解くべき一手”があるはずです。
どうか焦らず、丁寧に、まずその一つから始めてみてください。