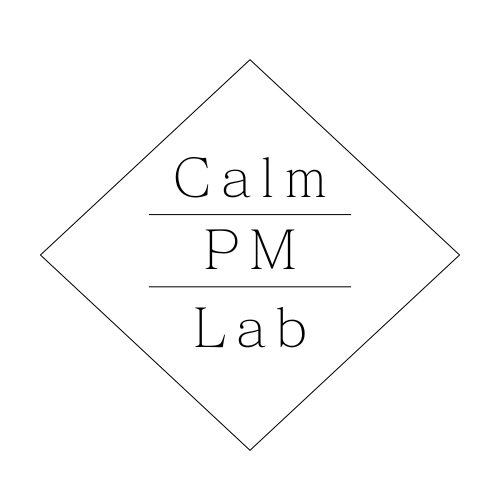プロンプト設計とプロジェクト設計 – 本質は同じ?
はじめに – なぜこの2つを比べてみたのか?
ClaudeやChatGPTなどの生成AIを使っていると、うまくいくときと、まったく期待外れな出力になるときがあります。
その差を分けるものは何か?
多くの場合、それはこちらが投げたプロンプト(指示文)の質です。
曖昧な問いを投げれば、曖昧な返答が返ってくる。
前提条件が足りないと、AIはまったく違う前提で答えてしまう。
このやり取りを繰り返すうちに、ふと思いました。
「これって、プロジェクトの設計とまったく同じでは?」
プロンプト設計とプロジェクト設計の間には、驚くほど多くの共通点があると感じたのです。
プロンプト設計とプロジェクト設計の共通点
まず何より大きいのは、ゴールが曖昧だと迷走するという点です。
「とりあえずいい感じにお願い」では、AIもうまく返してくれません。
これはプロジェクトでも同じで、「なんとなくやろう」で始まったものは、大抵うまくいきません。
また、インプットの質がアウトプットの質を決めるという点も重要です。
どんな情報を、どの順序で、どれくらいの粒度で渡すか。
それによって、AIの出力が劇的に変わります。
これは、プロジェクトにおける要件定義や関係者とのすり合わせと極めて近い構造です。
さらに、曖昧な依頼は“やり直し”を生むという点も見逃せません。
プロンプトが雑だと、こちらの意図とはまったく違う方向に話が進み、
結局「そうじゃない」と言って書き直してもらうことになる。
これは、タスクの指示や発注の仕方にも通じる学びです。
違いがあるとすれば、どこか?
もちろん違いもあります。
たとえば、AIは言語化された内容にしか反応しないという特性があります。
つまり、文脈・空気感・人間関係といった“暗黙知”には反応できない。
一方、プロジェクト設計においては、そうした非言語的な要素の調整こそがPMの本領だったりします。
また、プロンプトは基本的に1対1のやりとりですが、プロジェクトは**多人数での“意味の共有”**が求められます。
その分、関係者ごとの理解度や背景を考慮しながら進める必要がある。
それでも、共通点の多さは十分に示唆的だと思います。
PMがプロンプト設計から学べること
プロンプト設計を鍛えることは、PMに必要な情報整理力や構造化スキルの訓練になります。
たとえば、次のような要素を明確にする意識が求められます:
- ゴール(何を求めるのか)
- 制約(やってはいけないこと/予算や期間)
- 役割(誰に、どの視点で答えてもらいたいか)
- 背景(なぜそれが必要か)
- 例示(こういう形が望ましい)
これらは、プロンプトだけでなく、要件定義や報告、関係者への説明においても共通する構造です。
こうした整理に役立つのが、5W1Hのようなシンプルなフレームワークです。
- Who(誰に)
- What(何を)
- Why(なぜ)
- When(いつまでに)
- Where(どの文脈で)
- How(どうやって)
プロンプトを投げる前にこれらを意識するだけで、出力の精度は大きく変わります。
同じように、プロジェクト設計においても、こうした基本的な問いを丁寧に整理することが成果物の質を決定づけます。
そして、ここで必要になるのが整理整頓の力です。
混乱した指示からは、混乱した成果物しか生まれない。
これはAIに対しても、人に対しても、まったく同じです。
PMにとっての「整理整頓」とは、物理的な片付けだけでなく、
言葉・構造・意図・順序の“見える化”による混乱の除去を意味します。
そしてそのために最も有効なのは、“掃除”のような地味で確実な作業です。
情報を整える。背景を明示する。言葉を選び直す。
この積み重ねが、プロンプトの精度を高め、プロジェクトの混乱を防ぐ鍵になります。
おわりに – プロジェクトも、問いの質から始まる
プロンプトとプロジェクト。
一見まったく異なるものに見えて、その根底には共通した構造があります。
それは、
「問いの質が、成果の質を決める」
ということ。
AIを使いこなす訓練は、PMとしての設計力・言語化力・思考の構造化力を磨く訓練でもあります。
そして最後に、もうひとつ。
私がプロンプト設計を通じてあらためて思ったのは、AIにできなくて人間にできることとは何かという問いです。
その答えの一つは、こういうことではないでしょうか。
床に落ちたゴミに気づき、それを拾うこと。
みんなが自分の仕事に集中しているとき、
「誰の仕事でもないけれど、誰かがやらないといけないこと」に気づけるのは、
全体を見ている人間だけです。
そして、その“仕事にならない仕事”に意味を見出し、行動すること。
それはまさに、人間の仕事だと私は思います。
プロンプトもプロジェクトも、細部と全体、構造と意図、そして誰も見ていない“隙間”まで目を配れる人が、最終的に価値をつくっていくのだと信じています。