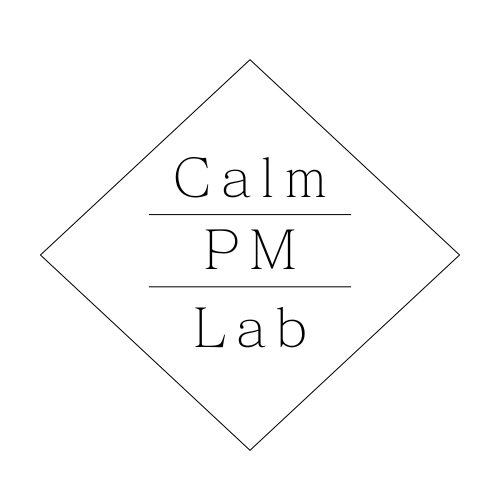その報告は何のため?
デイリーやウィークリーの進捗報告から、障害報告、予算消化報告に至るまで、プロジェクトを進行する中で、様々な報告業務が日々発生します。有史以前から当たり前のように行われている報告もあれば、PMとしてあなたが追加したもの、過去のトラブルの反省として顧客から求められるようになったものなど、種類も背景もさまざまです。
私はこれまでのPMとしての経験の中で、報告という業務がその目的を問われないまま、報告そのものが目的化していき、プロジェクトリソースを圧迫するのを何度も見てきました。特に誰もその報告の中身、クオリティに注意を払っておらず、報告されることに意味があるような報告業務がチームのリソースのみならず、モチベーションの削っていく場面を経験しています。例えば、納品するWebシステムの全てのページを画面キャプチャして、資料に貼り付けるといった虚無仕事にメンバーが駆り出されるようなことは、現在でも形を変えて行われ続けているでしょう。残念ながら。
それほどに、報告という行為は手段が目的化しやすく、思考停止で処理されやすい業務です。しかし、目的に寄与しない行為にリソースを割く余裕があるプロジェクトなど、この地球上に存在しないと考えれば、PMがこうした業務をそのまま看過するのは職務放棄に近いでしょう。
報告のコストは大きい
まず、一般に報告業務のコストは他の業務のコストに比べてとても低く見積られがちです。そのため、報告はよく精査されないまま増えていく傾向があります。しかし、報告コストは想像以上に大きなものです。
準備のコスト
どんな些細な報告であったとしても、情報収集など全くの準備なしで行えるものはないでしょう。なぜなら、そのような自明なものがもしあれば、それはそもそも報告の必要性がないものだからです。
さらに、単に報告するだけに留まらず、報告した後のリアクションへの対応なども考慮し始めると報告内容の順番や言い回しの精査といった(余計な)仕事も発生し、元々考えていた倍の時間がかかるといったことも珍しくないのです。
切り替えのコスト
報告業務は割り込みタスクとして発生することが多い業務です。それまでに進めていたタスクの中断を生みやすいタスクということです。これはタスクのスイッチングを発生させ、脳の集中を途切れさせ、フローを阻害します。報告自体のコストが仮に小さいかったとしても、他のタスクの生産性に与える影響は甚大なのです。
虚偽の安心を生むコスト
報告はうまく使うとルーティーンを生み出す効果が期待できます。ルーティーンは一般にはプロジェクトにリズムを生み、異常事態の早期検出にも役に立ちます。医療現場におけるバイタルチェックの徹底などにその顕著な効果を認めることができます。しかしながら、同時にデメリットとして、「報告されているから大事はない」といった認識にも陥りやすい面があります。何のための報告なのかを忘れてしまうと、報告があること自体に満足してしまいやすく、検知されるべきリスクを検知できないというコストが生まれるのです。
報告がどうしても避けえないものはPMが行う
報告も、プロジェクトの一環として行う以上は、プロジェクトの目的に寄与するものでなければいけません。そして、その精査を行う責任は、実際的に影響を及ぼせる権限の観点からもPMが担うことが多いでしょう。
そこで、報告業務は基本的にはPMが行うようにすることをお勧めします。こうすることで、
- 報告業務を減らすモチベーションがPM自身に生まれる
- (エンジニアやデザイナなどの)プロジェクトの貴重なリソースを報告業務に割くことを避けれる
- 報告を求める存在(顧客や上司、ふらっと訪れた役員など)が何を気にしているのかといった情報をPMが得ることができる
といったメリットを享受することができます。無意味な仕事は基本的に他者に振っている限りは減らそうとするモチベーションが湧かないものです。報告に限らず、実施する意味がよくわからない業務は一旦PMが受けるようにしましょう。そうして、プロジェクトメンバーを護るのです。そして、PMである貴方にも行う意味がわからない報告業務は勇気を持って無くしましょう。
意味のわからない仕事を断るのは、勇気ではなく職責です。
プロジェクトに意味を注入するのがPMの仕事であるならば、意味のない仕事は排除する。それがPMとしての正しい姿勢なのです。