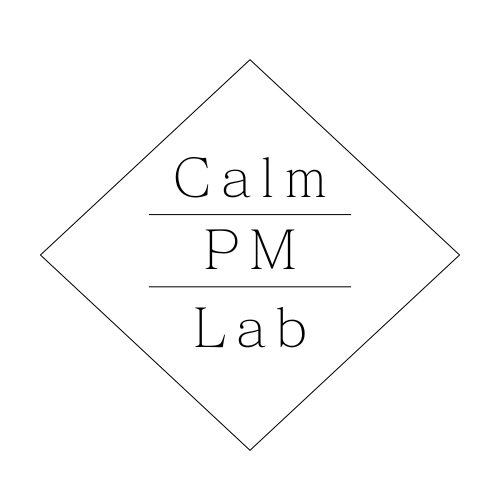立ち上げ前の“静かな違和感”を無視しない
プロジェクトの立ち上げ時点で違和感を感じることがあると思います。プロジェクトの目的が曖昧、不明、または存在しない。ステークホルダが不明、目的や期待値がバラバラ。納期ありきでとにかく早く開始させようとする。etc...
その他にも言語化できない「何だか嫌な感じ」も含め、PMはこうした違和感を無視してはいけません。具体的には違和感を一つ一つ丁寧に言語化を進めて、プロジェクトの開始前にこれらを解消する、解消できなければプロジェクトを止める必要があります。
プロジェクトが始まってしまうと、そこには「慣性」が働きます。すでに多くの人が関与し始めるため、簡単には止められず、軌道修正も難しくなってしまうのです。そのため、違和感はプロジェクトの開始前に解消する必要があるのです。
"違和感"の解像度をあげる
まず、大前提としてたとえ言語化できなくても、PMである貴方の違和感は間違っていません。これまでの経験と直感が貴方にアラートを投げかけるのであれば、それは正しいのです。しかし、そのままだと、周囲に納得してもらう形で違和感を解消することはできません。
そのため、まずは違和感の言語化を試みることになります。そのためにプロジェクト計画書を作成することをお勧めします。プロジェクト計画書を作成することで、自然と次のような効果を得ることができます。
- 目的の言語化
- ステークホルダの明示
- スコープの明示(やらないことの明示)
- リソースの明示
- 期待される納期とその理由の明示
プロジェクト計画書自体、ちゃんと存在することに大きな意義はありますが、ここでより強調したいのが、プロジェクト計画書を作る過程でプロジェクトの輪郭を明確にしていき、ステークホルダの合意を得ていくというプロセスの方です。
そして、もし、プロジェクト計画書が(ステークホルダの考えが違いすぎてなどで)作れない、作っても承認されないといった状態になるなら、そのプロジェクトは止めましょう。こうしたプロジェクトは必ずデスマーチの温床となり、貴方や貴方のチームを毀損します。
また、プロジェクト計画書を作っても、なお違和感が残る場合もあるでしょう。つまり、体裁の整った計画書が出来上がっているものの、誰もそれを信じていないし、本当の思惑は別にあるというケースです。この場合も本来はプロジェクトを止めるべきですが、「止めるための理由」が明文化できないケースが多くあります。こういう場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分けて、より解像度を高めると同時に、サブプロジェクトのみを開始して、関わる人間を限定しながら様子を見るという手法が使えます。
PMの仕事は"No"をいうこと
PMはプロジェクトに意味を注入するのが仕事です。そこから導かれることは、意味がないと判断されるプロジェクトには"No"を言うことが仕事になるということです。
そして、PMが最も"No"を言わなければいけないタイミングがプロジェクトの開始前であり、そのタイミングが一番言いやすいタイミングでもあるのです。最初に言うべき場面で"No"を言えなかったPMは、その後もずっと言えません。なぜなら、「最初にNoを言わなかった」ことの負債は、後になればなるほど重くのしかかってくるからです。
とはいえ、"No"をいうのが苦手な人もいるでしょう。私もそうです。そんな人にお勧めなのが、"No"を言うつもりで"Yes"を言うことです。この行為には二つ効果があります。一つは、心理面で"No"に慣れる効果。一つは、"Yes"を伝えるまでに「間」が発生し、その「間」が無言の"No"になるという効果です。騙されたと思ってやってみてください。人間は、言語以外にも多様なメッセージを発信していることがわかって面白いですよ。